


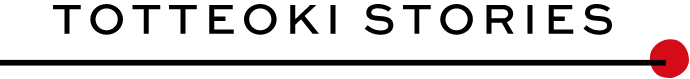

冒頭にルーシーさんは、「外国人に向けての日本のコンテンツはもう十分すぎるほどあります。大事なことはコンテンツをどう伝えるかです」と語りかけた。その前提でインバウンドの需要拡大を考える事業者たちに今やるべきことを2つ挙げたいという。ひとつは5年後の事業イメージを詳細に考えること。5年後どれくらいの人が、どれくらいの頻度で、どれくらいの金額を落とすのか、その未来予想図を訪日客のいない今描くべきだという。そしてもうひとつが、その5年後の描いた姿に向けて国内リソースを活用していくことだ。
ルーシーさんは外国人顧客を3つのレベルにわけている。ひとつが初来日で日本語が話せない観光客などでレベル1の顧客。お箸よりもフォーク派、座布団よりもイスを選択する人たちのことだ。そしてレベル2が訪日リピーターや日本を大好きな人たちと日本滞在2、3年で片言の日本語を話すグループ。そして最後のレベル3が長期滞在で日本通の人々。お箸も座布団も大丈夫で、出汁が鰹か昆布かまで気になるような人たちだとルーシーさんは分析する。

いま日本には230万人もの外国籍の人が住んでおり、インバウンド需要の拡大を図るのであれば、国内リソースともいえる彼ら、特にレベル3の人たちの力を借りないのはもったいないというのだ。今回のプロジェクトでも日本在住の外国人からのアドバイスを受けていたが、その戦略こそ正しく、むしろもっと活用すべきではなかったかという。
とはいえ、その230万人の市場にどうリーチすればいいのか。その方法としてルーシーさんが挙げたのが以下の3つの場所へのアプローチ。ひとつがターゲットと考えている国の「大使館」。そこに自分たちの情報を置いてもらおう。もうひとつは東京アメリカンクラブなどの「社交クラブ」、最後に日本にある各国の「商工会議所」だ。いずれも情報を置いてもらうように働きかけることは誰でもできることだという。もちろんSNSの活用も情報ソースのひとつだ。さらに、意外と日本の情報はうわべの情報しか伝わっていないというのでチャンスがあるとルーシーさんはいう。「外国人にとって日本にあるすべてのものが興味をそそられるものです。たとえば蕎麦屋の前に、なぜ、狸の置物があるのか?そんなとことにまで疑問を持っています。問題は、そうした疑問に満足する答えを得られていないことです。逆に言えば、もっと深い情報を与えることができれば、潜在顧客とのつながりを深めることができるはず」。エンゲージメントを深められれば、日本を愛し外国語を操る広告塔として世界へ発信してくれることもあり、レベル3の人たちを放っておく理由はない。コロナ禍だからこそ大事にしたい国内リソースだ。

後半のセッションでは、「カルチャー」部門の4つのプロジェクトとワンテーマに絞ったディスカッションを行った。ショーのデジタル化でB2BからB2Cへとマーケットが開かれ、海外へのアプローチもできるようになった日本ファッション・ウィーク推進機構からは、今後、海外顧客との接点も多くなるため「エンゲージのためのより深い情報をいかに届けるか」というテーマを挙げた。
ショーのことを一番語れるのがデザイナーだが、コンセプトの説明をすることはあっても、言葉の問題もあり、これまで海外ファンやメディアとの距離を縮めることは難しかった。ルーシーさんはこの問いに対し、デザイナーやデザイン、日本文化をよく知る通訳者、デザイナーの言葉を代弁できるようなガイド的な通訳が必要では、と提案した。
続いてパルコは、「インフルエンサーの活用」をテーマとして掲げた。日本のポップカルチャーを具現化した存在ともいえるパルコだが、知らない人たちにパルコを説明するのは至難の業だ。そのため、ファッション・ウィーク同様にパルコの背景や本質を顧客の属性にあわせて代弁できる人が必要ではないかという話になった。そのためにも投稿をシェアした人はどんな属性なのか。自分たちの通じたい人にきちんと届いているか、数でなく中身を検証することが重要であると結論付けた。インフルエンサーの難しさはフォロワーが多いから影響力があるわけではない、ということだ。
 JFW
JFW パルコ
パルコ 続く雪国観光圏とは、「ラグジュアリー」「富裕層」をテーマにした。雪国観光圏は旅館をラグジュアリーではなく文化体験施設と位置付けていると述べたが、ルーシーさん曰く、「旅館に対する外国人のイメージは非日常を体験する施設で、インスパイアされる場所です。高級な印象ももっています」という。「ただし、レベル1、2のお客さんには一泊目は布団でよいが、2泊目からはベッドで。畳での食事もよいですが、2日目からはテーブルと椅子で、というような需要にも応えられるような工夫は必要ではないか」とアドバイスした。
最後に、地域の産業である製造業でインバウンド拡大を狙う諏訪のいちきゅう蓼科は、ビジネスで来日する客をターゲットにしているため「オンとオフ」をテーマにした。国は違うがビジネストリップで来日すればビジネス寄りになるのは当然であるため、アクティビティよりは文化体験、例えば禅の体験などが日本文化を知れてよいのではないか、あるいは工場見学も今後のビジネスにつながる可能性もあるのではないか、など、小さな気づきを得られるセッションとなった。
最後にルーシーさんは、改めて「日本に必要なのはいかに伝えていくか」そこを大事にして、徐々に戻ってくるインバウンド客を迎えて欲しいとセミナーを終えた。
 雪国観光圏
雪国観光圏 いちきゅう蓼科
いちきゅう蓼科ルース・マリー・ジャーマン(ルーシー)氏
株式会社ジャーマンインターナショナル 代表取締役社長
木村 ともえ
ファシリテーター /株式会社ジェイアール東日本企画
ソーシャルビジネス開発局